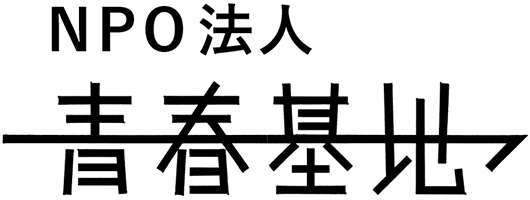TANKEN探究総合研究所
Tanq Research Institute.

TANKENとは、専門性の違う多様なメンバーと共に、「教育の再定義」の手がかりを見つけていく研究所です。
日々の現場での実践や、組織のなかでの実験から、問いや葛藤、ときに手応えを取り出し、ナラティブに研究しています。
複雑なものを複雑なままに、ままならなさとともに動的に進めています。
研究の全体像

DIALOGUE(対話する)
いつも中心にあるのが対話です。多様な世代や立場のひとたちとオープンに対話をすることで、新しい視点や感覚・暗黙知を取り出したり、一緒にうなったりします。仮説を立てて分析するというよりも、ナラティブアプローチと言って臨床から捉えていきます。
DIGGING(ディグる)
事例や先行研究を調べたり、データや制度などマクロな視点から捉えるために、リサーチやフィールドワークも適宜実施。異なる視点を見つけたり、取り出した暗黙知の代表性を深めたりしていきます。
GENERATION(生成する)
これらから生まれてきたもの・見えてきた視点は、実際に「やってみます」。
研究にふれる

生成ってなに?
「生成/Generative Pedagogy」とは、研究の土台にあるキーワードです。
私たちが教育を考えるときの基盤となる考え方であり、研究対象でもあります。

生成の森
生成される場とは、どんな場なのか。チームのなかで起きてきた現象や感覚をまとめてみました。森を散策するように覗いてみて下さい。

イベント
不定期ではありますが、さまざまな分野の人たちとのオープンダイアローグやイベントを開催しています。

note
TANKENのなかで見えてきたことや、日々の学びづくりについて、noteにて発信しています。
チームメンバーによる関連の研究リスト
石黒和己『 VUCAの時代における「想定外の未来をつくる」学び−PBLによる発達論から生成論への転換−』
東京大学教育学研究科修士論文
酒井朝羽『 教師が探究心を身につけるための環境要因の分析−高等学校におけるPBL実践を事例に−』
信州大学教職大学院実践研究書
佐野真知子『 公立高校におけるクリエイティブワークショップの実践−総合的な探究の時間におけるテーマ設定の手がかりとして−』
横浜国立大学教育デザインフォーラム
石黒和己『ウェルビーイングな学校にむけて 生成の教育学と SEL の公立高校での実践』
https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/journal/.assets/SFCJ22-2-25.pdf
慶応SFC学会『KEIO SFC JOURNAL Vol.22 No.2』2023.03 発行
※2023年4月更新